脱・米中依存!スイス国産AI「Apertus」の全貌
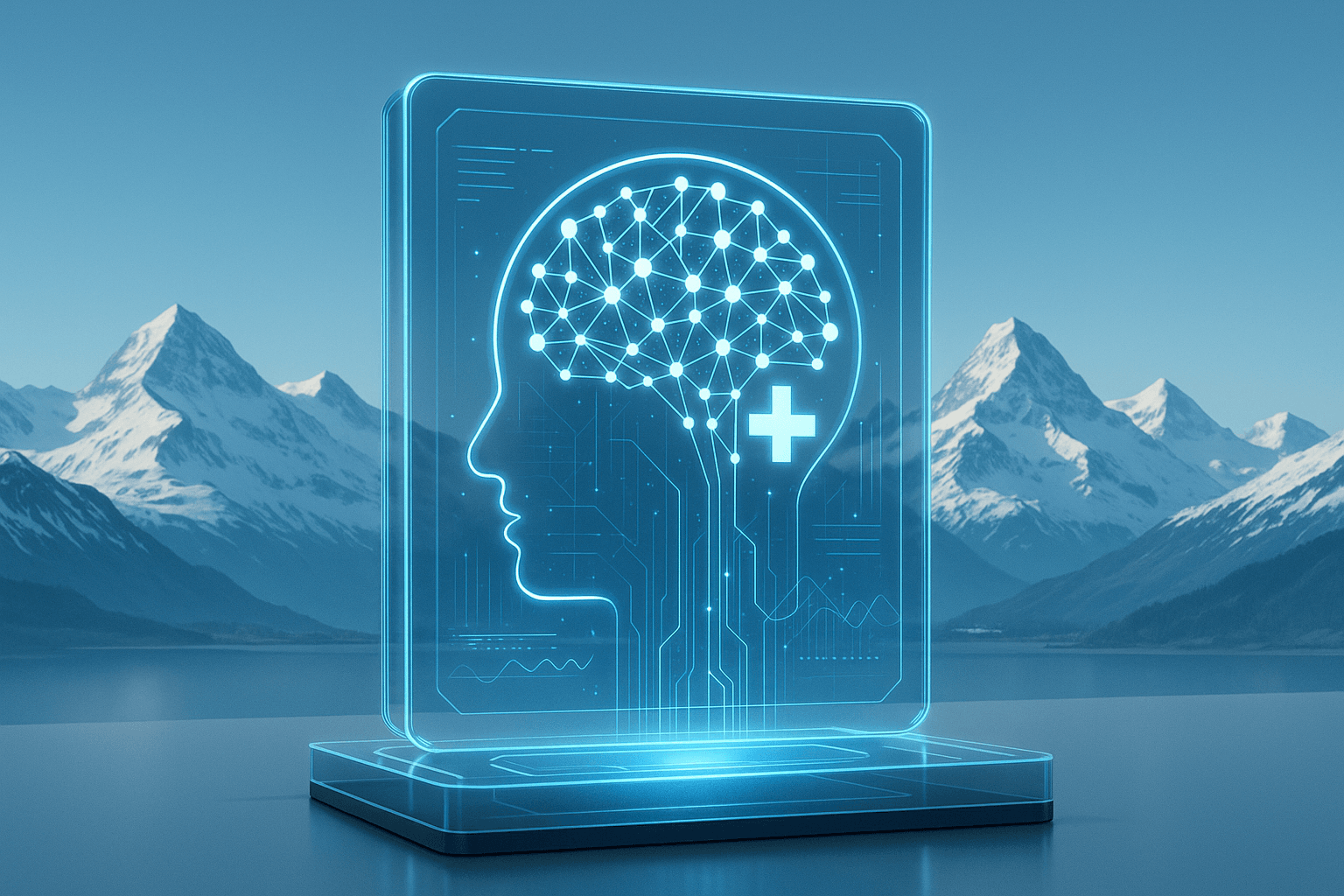
目次
ChatGPTの利用料金値上げに悩んでいませんか?特定企業のAIサービスに依存するリスクを感じていませんか?そんな課題を解決する可能性を秘めた革新的なAIが、スイスから登場しました。完全無料で商用利用も可能な国家主導のオープンソースAI「Apertus」です。EU規制にも完全対応し、金融・医療分野でも安心して利用できる信頼性を備えています。この記事では、Apertusがもたらすビジネスチャンスと、日本企業への影響について詳しくご紹介します。
1. スイスが国家レベルで開発したオープンソースAI「Apertus」とは
2025年9月、スイスからAI業界を揺るがす画期的な発表がありました。それが、国家レベルで開発された完全オープンソースの大規模言語モデル(LLM)「Apertus」です。このプロジェクトは、単なる新しいAIモデルの登場にとどまらず、AI開発のあり方、そして国家とテクノロジーの関係性に一石を投じるものです。これまでAI開発の最前線は、OpenAIやGoogleといった巨大テック企業が牽引してきましたが、Apertusはそれらとは一線を画し、公的機関が主導することで「デジタル主権」を確立しようという壮大な試みです。本セクションでは、このApertusがどのようなものなのか、その基本概要から開発の背景、そして技術的な特徴までを詳しく解説していきます。
出典:Switzerland Releases Apertus, a National Open-Source AI Modellink
1-1. Apertusの基本概要と開発背景
Apertusは、スイスの主要な公的学術機関が結集して生み出した、国家的なAIインフラプロジェクトです。その根底には、AI技術が社会の基盤となる中で、その開発と利用を一部の外国企業に依存することへの強い懸念があります。特に、金融や医療、行政といった機密性の高い情報を扱う分野において、透明性と信頼性が確保されたAIの必要性は論を俟ちません。Apertusは、こうした課題に対するスイスの答えであり、企業主導のプロプライエタリなAIモデルに対する、信頼できる公的な代替案として設計されました。この動きは、スイスが自国のデジタルデータを自国の管理下に置き、AI技術の恩恵を国民全体で享受しようとする、明確な国家戦略の表れと言えるでしょう。
1-1-1. EPFL、ETH Zurich、CSCSによる共同開発
Apertusの開発は、スイスが世界に誇る3つのトップ機関によって主導されています。ローザンヌ連邦工科大学(EPFL)、チューリッヒ工科大学(ETH Zurich)、そしてスイス国立スーパーコンピューティングセンター(CSCS)です。これらは、それぞれがAI、コンピューターサイエンス、そして高性能計算の分野で世界最高峰の研究機関であり、その知見とリソースを結集することで、Apertusという野心的なプロジェクトが実現しました。EPFLとETH ZurichがAIモデルの設計と学習を主導し、CSCSがその膨大な計算処理を支えるという、まさに産学官ならぬ「学・学・官」連携の理想的な形がここにあります。この強力な布陣は、Apertusが単なる実験的なプロジェクトではなく、長期的な視野に立った国家的な取り組みであることを示しています。
1-1-2. 国家デジタル主権戦略の一環として位置づけ
Apertusは、スイスの「デジタル主権(Digital Sovereignty)」戦略の核心をなすプロジェクトです。デジタル主権とは、国家が自国のデジタル空間におけるデータ、インフラ、そして法規制を自律的に管理・コントロールする能力を指します。現代社会において、AIは経済活動から国民生活、安全保障に至るまで、あらゆる側面に影響を及ぼす基盤技術となりつつあります。そのため、このAI技術を外国の特定企業に依存することは、経済的な従属だけでなく、国家の意思決定の自由を損なうリスクをもたらします。Apertusの開発は、スイスがこのリスクを深刻に受け止め、自国の価値観と法規制に基づいたAIエコシステムを構築しようとする強い意志の表れです。これは、他国にとっても、自国のデジタル主権をいかにして確保するかを考える上で、重要なモデルケースとなるでしょう。
1-1-3. 企業主導AIの課題
現在、高性能なAIモデルの多くは、OpenAI、Google、Metaといった米国の巨大テック企業によって開発・提供されています。これらのモデルは非常に強力である一方、その学習データやアルゴリズムの内部はほとんど公開されておらず、「ブラックボックス」と化しています。このような状況は、いくつかの深刻な問題を引き起こします。第一に、アルゴリズムに潜むバイアスや公平性の問題を検証することが困難です。第二に、企業側の都合でサービス内容が変更されたり、利用料金が一方的に引き上げられたりするリスク(ベンダーロックイン)があります。そして第三に、機密情報や個人データを扱う際に、そのデータがどのように利用されるかについての懸念が拭えません。Apertusは、こうした企業主導AIの課題に対する明確なアンチテーゼとして登場しました。公的機関が開発・管理し、その全てをオープンにすることで、透明性、信頼性、そして長期的な安定性を確保することを目指しているのです。
2. 完全オープンソース化という革新性
Apertusの最大の特徴は、その徹底した「オープンソース」へのこだわりにあります。これまでも「オープンソース」を謳うAIモデルは存在しましたが、その多くは学習済みのモデルのウェイトを公開するにとどまり、そのモデルがどのようなデータで、どのように学習されたのかという最も重要な部分がブラックボックスのままでした。Apertusは、この常識を覆し、モデルのウェイトだけでなく、学習に用いたデータ、そして学習プロセスそのものに至るまで、全てを公開するという、前例のないレベルの透明性を実現しました。この「完全オープンソース化」は、単に技術的な情報を公開するという以上の、AI開発のパラダイムシフトを促すほどの革新性を秘めています。本セクションでは、この革新性が具体的に何を意味するのかを、従来のモデルとの比較や、先進的な法規制への対応という観点から深掘りしていきます。
出典:Switzerland Releases Apertus, a National Open-Source AI Modellink
2-1. 従来のAIモデルとの透明性の違い
Apertusが実現した透明性は、従来のAIモデルとは一線を画します。例えば、Meta社が提供するLlamaシリーズは、オープンソースAIの代表格とされていますが、その学習データの詳細は完全には公開されていません。そのため、研究者や開発者がモデルの挙動を完全に理解し、潜在的なバイアスや脆弱性を検証することは困難でした。Apertusは、この課題に正面から向き合いました。学習データの全貌を明らかにすることで、誰でもその内容を精査し、モデルの特性を根本から理解することを可能にしたのです。これは、AIの信頼性と安全性を確保する上で、極めて重要な一歩と言えます。さらに、学習プロセスそのものを公開することで、他の研究者がその結果を再現し、さらなる改良を加えることも容易になります。このような徹底した情報公開こそが、Apertusを真に「オープン」なAIたらしめているのです。
2-1-1. ウェイト、データ、学習プロセスの全てを公開
Apertusの「完全オープンソース」は、具体的に3つの要素から成り立っています。第一に「オープンウェイト」。これは、学習済みのAIモデルのパラメータ(ウェイト)を公開することです。これにより、誰でもモデルをダウンロードし、自分の環境で実行することができます。第二に「オープンデータ」。これは、モデルの学習に使用された全てのデータを公開することです。これにより、モデルがどのような知識を持ち、どのような偏りを持つ可能性があるのかを分析できます。そして第三に「オープントレーニング」。これは、データの前処理からモデルの学習、評価に至るまでの全プロセスを記録した「学習レシピ」やスクリプトを公開することです。これら3つが揃うことで初めて、AIモデルの完全な再現性と検証可能性が担保されます。Apertusは、この3つの要素を全て満たすことで、AI開発における透明性の新たなゴールドスタンダードを打ち立てたのです。
2-1-2. 中間チェックポイントと再構築スクリプトの提供
Apertusの透明性へのこだわりは、さらに細部にまで及びます。プロジェクトチームは、最終的なモデルだけでなく、学習の途中段階で保存された「中間チェックポイント」をも公開しています。これは、AIモデルがどのようにして徐々に知識を獲得し、能力を発展させていくのかという、学習のダイナミクスを研究する上で非常に貴重なデータとなります。例えるなら、完成した絵画だけでなく、その制作過程のスケッチや下書きも全て公開するようなものです。さらに、これらのチェックポイントからモデルを再構築するためのスクリプトも提供されているため、研究者は特定の学習段階から独自の実験を開始することも可能です。このような徹底した情報提供は、AI研究の加速と、より深いレベルでのモデル理解を促進するものであり、Apertusが単なるツール提供にとどまらず、学術コミュニティ全体の発展に貢献しようとする姿勢の表れと言えるでしょう。
2-1-3. Apache式ライセンスによるイノベーション促進
オープンソースプロジェクトの成功において、ライセンスの選択は極めて重要です。Apertusは、そのライセンスとして「Apache License 2.0」に近い、非常に寛容な(permissive)ライセンスを採用しました。このライセンスの最大の特徴は、学術研究目的だけでなく、商用利用も原則として自由に認められている点にあります。これにより、スタートアップ企業から大企業まで、あらゆる組織がApertusを自社の製品やサービスに組み込み、新たなビジネスを創出することが可能になります。公的機関が開発した最先端のAI技術を、民間企業が自由に活用し、イノベーションを加速させる。この好循環を生み出すことこそが、Apertusプロジェクトの狙いの一つです。透明性と信頼性を確保した上で、経済的な発展にも貢献するという、オープンソースの理想的な形を追求しているのです。
3. 国家主導AI開発の戦略的意義
Apertusの登場は、単なる技術的な成果にとどまらず、地政学的な観点からも大きな戦略的意義を持っています。これまで、最先端のAI開発は米国の巨大テック企業が独占し、それに中国が国家主導で猛追するという構図が続いてきました。この米中二極体制の中で、他の国々は、両国のプラットフォームの「利用者」という立場に甘んじるか、あるいは独自の道を模索するかの選択を迫られています。スイスがApertusで示したのは、明確に後者の道です。国家が主導し、学術機関と連携することで、米中のいずれにも依存しない、独自のAI環境を構築するという選択です。この動きは、AI時代における「第三極」の可能性を示唆するものであり、世界中の国々のAI戦略に影響を与えることは必至です。本セクションでは、この国家主導AI開発が持つ戦略的な重要性を、デジタル主権と国際関係という2つの側面から深く考察します。
出典:Switzerland Releases Apertus, a National Open-Source AI Modellink
3-1. デジタル主権確立への道筋
デジタル主権の確立は、現代国家にとって喫緊の課題です。Apertusは、その具体的な道筋を示す画期的な事例と言えます。自国でAIモデルを開発・管理することは、外国企業への技術的・経済的な依存から脱却し、自国のデータを国内で安全に管理・活用するための第一歩です。特に、AIが軍事技術やサイバーセキュリティに応用される現代において、AI技術の自律性を確保することは、国家の安全保障に直結します。Apertusのように、AIを道路や電力網のような「公共インフラ」として位置づけるという発想は、非常に重要です。これにより、AI技術の恩恵を一部の企業や富裕層だけでなく、国民全体で公平に享受し、社会全体の発展に繋げることが可能になります。スイスのこの試みは、AI時代における国家の役割を再定義するものと言えるでしょう。
3-1-1. 外国企業依存からの脱却
多くの国では、AIサービスの利用は、特定の外国企業、特に米国の巨大テック企業への依存を深める結果となっています。これは、経済的な富の流出に繋がるだけでなく、自国の産業の競争力を削ぐ要因ともなり得ます。例えば、国内のスタートアップが革新的なAIサービスを開発しようとしても、その基盤となるAIモデル自体が外国企業にコントロールされていては、自由な発想や迅速な開発が阻害される可能性があります。Apertusは、この「デジタル的従属」からの脱却を目指すものです。自国で開発したオープンな基盤モデルを提供することで、国内の企業や研究者が、その上で自由にイノベーションを追求できる環境を整える。これにより、国内に健全なAIエコシステムが育ち、結果として国全体の技術力と経済力の向上に繋がることが期待されます。
3-1-2. 国家安全保障とAI技術
AI技術は、現代の国家安全保障において、決定的に重要な役割を担いつつあります。情報戦、サイバー攻撃、自律型兵器など、AIの軍事利用は急速に進展しています。このような状況下で、基幹となるAI技術を他国に依存することは、自国の安全保障上の重大な脆弱性となりかねません。例えば、敵対国がAIモデルの供給を停止したり、モデルにバックドアを仕込んだりするリスクも理論的には考えられます。Apertusのような国家主導のAI開発は、こうしたリスクに対する直接的な対抗策となります。自国で管理・検証できる透明性の高いAIを持つことは、防衛やインテリジェンスの分野において、自律性を保ち、外部からの不当な干渉を排除するための不可欠な要素です。AI時代の安全保障は、技術的な自立と不可分に結びついているのです。
3-1-3. 公共インフラとしてのAI
Apertusプロジェクトの根底に流れる思想で特に注目すべきは、AIを「公共インフラ」として捉える視点です。これは、AIがもたらす恩恵は、一部の私企業に独占されるべきではなく、社会全体で分かち合われるべき公共財であるという考え方です。道路、水道、電力といった従来の社会インフラが、国民の生活と経済活動の基盤となっているように、AIもまた、現代社会における新たな基盤インフラであると位置づけられています。この考えに基づけば、AIの開発・提供・管理に公的機関が責任を持つことは、ごく自然な帰結と言えます。Apertusは、その理念を具現化したものであり、AIの民主化、すなわち、誰もがAI技術にアクセスし、その恩恵を受けられる社会を実現するための重要な一歩となる可能性を秘めています。
4. 日本のAI戦略への示唆と教訓
スイスのApertusプロジェクトは、遠いヨーロッパの国の話として片付けることはできません。むしろ、AI技術の活用と開発において同様の課題を抱える日本にとって、多くの示唆と教訓を与えてくれる貴重なケーススタディです。日本は、世界有数の経済大国でありながら、最先端のAI開発、特に大規模言語モデルの分野では、米国や中国に大きく後れを取っているのが現状です。国内のAI利用の多くを海外のプラットフォームに依存しており、デジタル主権の観点から見ても、決して安泰とは言えません。Apertusが示した国家主導のオープンソースAIというアプローチは、日本の現状を打破し、独自のAI戦略を再構築するための重要なヒントを提示しています。本セクションでは、日本のAI戦略が直面する課題を分析し、Apertusのモデルを日本に適用する可能性について考察します。
出典:Switzerland Releases Apertus, a National Open-Source AI Modellink
4-1. 日本の現状と課題
日本のAI戦略における最大の課題は、海外、特に米国企業への過度な依存です。多くの企業や研究機関が、OpenAIのGPTシリーズやGoogleのGeminiといった海外製のAIモデルをサービスの基盤として利用しています。これは、迅速にAIを導入できるというメリットがある一方で、長期的に見れば、技術的な主導権を失い、経済的な富が海外に流出し続けるという深刻なデメリットを伴います。国産AIの開発も進められてはいますが、学習データの量や計算資源の規模で海外勢に太刀打ちできず、限定的な成功にとどまっているのが実情です。また、スイスのApertusプロジェクトが示したような、政府、学術機関、そして企業が一体となった強力な連携体制が、日本ではまだ十分に構築されていない点も、大きな課題と言えるでしょう。
4-1-1. 海外AI依存の現状
現在の日本は、AIにおける「デジタル植民地」になりかねない岐路に立たされています。ビジネスの現場から個人のスマートフォンまで、私たちの周りにあるAIサービスの多くは、その心臓部を海外製のAIモデルに依存しています。これは、国内のデータが海外のサーバーに送信され、外国の法律や企業のポリシーに基づいて処理されることを意味します。経済産業省の調査でも、多くの日本企業がAI導入に際して海外のクラウドサービスを利用している実態が明らかになっています。この状況が続けば、国内のAI産業は、海外プラットフォームの下請け的な位置づけから抜け出せず、独自の競争力を失っていく恐れがあります。Apertusの挑戦は、こうした現状に警鐘を鳴らし、技術的自立の重要性を改めて問いかけています。
4-1-2. 国産AI開発の遅れと原因
日本でも、理化学研究所の「富岳」を活用したLLM開発など、国産AIの開発プロジェクトは存在します。しかし、その規模や性能は、残念ながら世界のトップレベルには及んでいません。その要因は複合的です。まず、学習に必要な計算資源(GPU)の確保が困難であること。次に、学習データの質と量が不足していること。特に、日本語の高品質なデジタルテキストデータが、英語に比べて圧倒的に少ないことが大きな足かせとなっています。さらに、AI開発を担うトップレベルの人材が、国内よりも海外の企業や研究機関に流出しているという問題も深刻です。これらの課題を克服するためには、個別の企業や研究機関の努力だけでは限界があり、国家レベルでの戦略的な投資と、長期的な視点に立ったエコシステム構築が不可欠です。
4-1-3. 政府・学術機関・企業の連携不足
スイスのApertusが成功した大きな要因の一つは、政府のビジョン、学術機関の研究能力、そしてCSCSのような公的な計算インフラが、一つの目標に向かって緊密に連携したことにあります。翻って日本の状況を見ると、政府、大学、企業が、それぞれ独自にAI開発に取り組んでいるものの、その連携はまだ十分とは言えません。政府は戦略を掲げるものの、具体的なプロジェクトへの落とし込みが遅れがちです。大学の研究成果が、必ずしも産業界での実用化に結びついていません。企業は目先の利益を優先し、基礎研究への長期的な投資には及び腰です。この「縦割り」の構造を打破し、Apertusのような強力な産学官連携、あるいは「学・学・官」連携の体制をいかにして構築するかが、日本のAI戦略の成否を分ける鍵となるでしょう。
5. 企業・開発者にとっての実用的価値
Apertusは、国家戦略や学術研究といったマクロな視点だけでなく、現場でAIを活用する企業や開発者にとっても、非常に大きな実用的価値を持っています。これまでの高性能AIモデルは、そのライセンス料が高額であったり、利用規約が厳しかったり、あるいは技術的な詳細が不透明であったりと、ビジネスで利用するには多くのハードルがありました。Apertusは、これらの障壁を取り払い、誰もが最先端のAI技術を、より自由に、そして安心して活用できる道を開きます。特に、コンプライアンスが厳しく求められる金融や医療分野の企業や、独自のAIサービスを開発したいスタートアップにとって、Apertusはまさに待望の選択肢となるでしょう。本セクションでは、この実用的価値を、ビジネス活用のメリットと、技術者・研究者への影響という2つの側面から具体的に解説します。
出典:Switzerland Releases Apertus, a National Open-Source AI Modellink
5-1. ビジネス活用の具体的メリット
企業がApertusを導入するメリットは多岐にわたります。最大の利点は、コンプライアンスに関する負担が大幅に軽減されることです。EUのAI Actのような厳しい規制にも対応できるように設計されているため、企業は法的なリスクを心配することなく、AI活用に集中できます。また、オープンソースであるため、自社のニーズに合わせてモデルを自由にカスタマイズ・改良できる点も大きな魅力です。特定のベンダーのプラットフォームに縛られる「ベンダーロックイン」のリスクからも解放されます。これにより、企業は自社のビジネスに最適化された、独自のAIソリューションを構築し、競争優位性を確立することが可能になります。初期コストやライセンス料を抑えられるため、これまでAI導入をためらっていた中小企業にとっても、新たなチャンスが広がるでしょう。
5-1-1. コンプライアンス負担の軽減
近年、AIの利用に関する法規制は、世界的に強化される傾向にあります。特に、2024年に成立したEUの「AI 法」は、AIの透明性や説明責任について厳格な要件を課しており、違反した企業には巨額の罰金が科される可能性があります。多くの企業にとって、この複雑な法規制への対応は、AI導入の大きな障壁となっています。Apertusは、この課題に対する明確なソリューションを提供します。開発段階からAI 法の要件を完全に満たすように設計されており、その透明性に関する資料も全て公開されています。そのため、Apertusを基盤としてAIサービスを構築する企業は、コンプライアンスに関する監査や報告の負担を大幅に削減できます。これは、特に規制の厳しい金融、医療、公共サービスといった分野で事業を展開する企業にとって、計り知れない価値を持つでしょう。
5-1-2. カスタマイズ・改良の自由度
プロプライエタリなAIモデルでは、提供されたAPIを通じてモデルを利用するしかなく、その内部構造に手を入れることはできません。そのため、自社の特定の業務に最適化したり、独自の機能を追加したりするには限界がありました。一方、Apertusは完全なオープンソースであるため、企業はモデルのソースコードにアクセスし、自社のニーズに合わせて自由にカスタマイズやファインチューニングを行うことができます。例えば、特定の業界の専門用語を学習させたり、自社の顧客データで追加学習を行なって応答精度を高めたりすることが可能です。この高い自由度は、企業が他社との差別化を図り、真に価値のある独自のAIサービスを創出するための強力な武器となります。
5-1-3. ベンダーロックイン回避
特定の企業のAIプラットフォームに深く依存してしまうと、その企業の料金体系やサービス内容の変更に、自社のビジネスが大きく左右されることになります。これを「ベンダーロックイン」と呼び、多くの企業が懸念するリスクの一つです。例えば、ある日突然、APIの利用料金が大幅に値上げされたり、重要な機能が廃止されたりする可能性もゼロではありません。Apertusのようなオープンソースのモデルを利用すれば、このベンダーロックインのリスクを根本的に回避できます。モデルは自社の管理下に置かれ、特定の企業の方針に縛られることはありません。これにより、企業は長期的な視点に立って、安定したAI戦略を推進することが可能になるのです。
6. まとめ
スイスが打ち出した国家主導のオープンソースAI「Apertus」は、AI開発の歴史における重要な転換点となる可能性を秘めています。これまで米中の巨大テック企業が牽引してきたAI開発の潮流に、国家が「公共インフラ」としてAIを位置づけ、透明性と信頼性を最優先する新たなアプローチを提示したからです。
Apertusの核心は、その徹底した透明性にあります。モデルのウェイトだけでなく、学習データ、学習プロセスに至るまで全てを公開することで、企業主導AIの抱える「ブラックボックス」問題に正面から挑みました。これは、AIの信頼性を担保するだけでなく、世界中の研究者や開発者が協力し、イノベーションを加速させるための強固な基盤となります。また、EUのAI 法といった厳しい法規制に準拠した設計は、コンプライアンスを重視する企業にとって、安心して利用できるという絶大なメリットをもたらします。
この動きは、日本にとっても他人事ではありません。海外プラットフォームへの依存という課題を抱える日本にとって、Apertusは「デジタル主権」を確立するための具体的なモデルケースを示しています。政府、学術機関、企業が連携し、日本語に最適化された高品質なオープンソースAIを開発することは、日本の国際競争力を維持・向上させる上で不可欠な戦略となるでしょう。
Apertusが示した道は、AI技術が一部の巨大企業の独占物ではなく、誰もがアクセスし、その恩恵を受けられる「民主化」された未来です。このスイスの小さな、しかし壮大な実験が、世界のAI開発にどのような影響を与えていくのか、今後も目が離せません。
よくある質問(Q&A)
Q1: Apertusは本当に無料で利用できるのですか?
A1: はい、Apertusは完全に無料で利用できます。Apache License 2.0に近い寛容なライセンスを採用しており、学術研究目的だけでなく、商用利用も原則として自由に認められています。企業がApertusを自社の製品やサービスに組み込んで新たなビジネスを創出することも可能です。ただし、利用に際してはライセンス条項を確認し、適切な帰属表示を行うことが推奨されます。また、Swisscom、Hugging Face、Public AIといった複数のプラットフォームを通じてアクセスできるため、技術的なハードルも低く設定されています。
Q2: 日本でもApertusのような国家主導のAI開発は可能でしょうか?
A2: 技術的には十分可能ですが、いくつかの課題があります。まず、スイスのように政府、学術機関、計算インフラが一体となった強力な連携体制の構築が必要です。日本には理化学研究所の「富岳」のような世界トップクラスのスーパーコンピューターがありますが、AI専用の大規模計算資源の確保と、長期的な投資計画が重要になります。また、日本語の高品質なデジタルテキストデータの収集・整備、AI開発人材の確保と育成、そして何より政府の明確なビジョンと継続的なコミットメントが不可欠です。スイスの成功例を参考に、日本独自のアプローチを検討する価値は十分にあります。
Q3: Apertusを使うことで、企業にはどのようなメリットがありますか?
A3: Apertusを活用する企業には多くのメリットがあります。第一に、コンプライアンス負担の大幅な軽減です。EU AI Actなどの厳しい規制に準拠して設計されているため、法的リスクを心配することなくAI活用に集中できます。第二に、ベンダーロックインの回避です。特定企業のプラットフォームに依存することなく、自社のニーズに合わせて自由にカスタマイズできます。第三に、コスト効率性です。高額なライセンス料を支払うことなく、最先端のAI技術を利用できます。第四に、透明性と信頼性です。モデルの内部構造が完全に公開されているため、安心してビジネスクリティカルな用途に活用できます。これらの利点により、特に規制の厳しい金融・医療分野や、独自のAIサービスを開発したいスタートアップにとって、Apertusは非常に魅力的な選択肢となります。